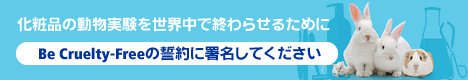「死んだ金魚をトイレに流すな」

死んだ金魚をトイレに流すな―「いのちの体験」の共有 (集英社新書)
- 作者: 近藤 卓
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2009/02
- メディア: 新書
なんだか衝撃的なタイトル。思わず買って一気に読んでしまいました。家で飼っていた金魚が死んだとき、トイレに死体を流す人がいることも衝撃ですが、北米ではそっちのほうが普通というのも驚きました。それでも著者は、もちろん子どもがいる家庭で金魚の死体をトイレに流すようなことはしていはいけないと書いています。ほっ。
私は、子どもたちにいのちについて教えると聞くと、どうしても生き物を殺してみさせて教えようとする手法のことを連想してしまうのですが、著者の観点はそういうところにはなくて(ホッ)、まず自分のいのちの大切さを実感させることが大事だという話につながっていくのでした。
その本論のところはこのブログのテーマとはすこしそれるので、ここではあまり触れずにぜひ本の方を読んでいただきたいとして、私が気になってしまうのは、やはり人以外の生き物に関係する話のあたり。
「虫を殺していのちの神秘を知ろうとしていた子どもが、それを放棄し、自らのいのちの重みを知っていく過程には、ある分岐点がある。それは一〇~一二歳の頃、明確な分かれ道となって訪れる。」
子どもが虫などの生き物に残酷なことをしてしまうのは、やはり普通にあることなわけですが、それは生きていることの秘密を知りたいという欲求に基づいているのだそうです。でもそれは、成長とともに自然にしなくなること。
「こんなふうに子どもたちは、虫や生き物を虐待したり殺したりすることで、いのちの秘密を知りうるのだろうか。
それは不可能なことである。子どもが一人でいのちの核心を探り出そうと、虫や生き物を殺し続けると、人は悲劇的で絶望的な営みに入り込んでしまう可能性があると、フロムも警告を発している。
(中略)
いのちとは何だろうと考えはじめたら、最終的に行き着くところは、実際に人を殺してみることしかなくなるのだ。」
この本に解剖の授業やサイエンスで犠牲になる動物たちのことが書かれているわけでは全くありませんが、人間のそういった自然な発達過程のことを考えると、「一〇~一二歳の頃」という、あるべきときを過ぎた中学生や高校生に、わざわざマウスやラットを殺させる授業をすることで「いのちの大切さ」が教えられると考えるのは、やはり何かがおかしいのではないかと感じます。
人生の分岐点で別々の道に分かれた人たちと議論しているのだから不毛なのだとも気づかされますが…
ちなみに、フロムは「いのちの秘密を極端にまで押し進めると、サディズムになる」とも言っているそうです。生命科学は、まさに「いのちの秘密を極端にまで押し進める」学問ですから、その一手段である動物実験についてもこの分析は当たるのではないかと思います。社会的な理由付けがあるかないかだけの違いだけで。(究極のところは人体実験→殺人ということを指すのだろうと思いますが)
と、少しそれましたが…
いずれにしても、「いのちの大切さ」はもちろん教えるべきものだけど、「いのちは大切」という文言をとなえれば教えられるものではないと常々思っているので、同様のことが書かれていた点でもこの本には共感しました。
そして、単に家に動物や生き物がいれば他者への共感を教えられるものでもないというところも同感です。身近な大人が、感じ取り方を教えてあげないとダメ。本当にそう思います…。虐待に近いまでに動物をほったらかしておいて共感もない親が子どもに教えることは、むしろいのちの大切さとは逆のことだと思います。
とはいえ、きっとこの著者だって別に動物愛護家だったりベジタリアンだったりはしないだろうなぁと思うわけですが、でももう一つ「グッ」とくるところがありました。
それは、現実の世界にはどうしようもなくいのちの重みには軽重があるということについてです。もちろん私たちは少しでもそれを変えたいとは思っているわけですが、でもこの分析は正しいと思います。
「こうした考え方には反論もあるだろう。大切ないのちを殺して食べるからこそ、『いのちをいただきます』と感謝の気持ちを育てるのだと。しかし、これも詭弁である。」
嗚呼、なんて痛快!!
そう思います。人はおそらく、心の整理をつけるための詭弁が必要なのです。